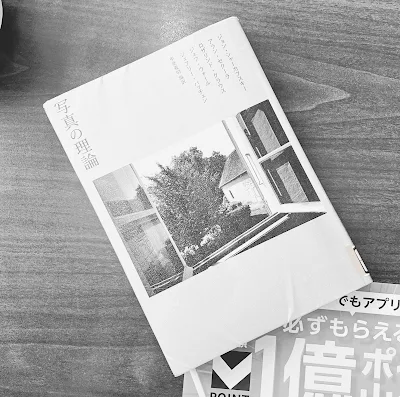「写真の理論」 甲斐 義明 (編訳) 2
● アラン・セクーラ
知らない世界の話を読む理解するのは、食べなれない料理を口にする時くらいに、怖く、わからず、しかし美味しいと感じられれれば、それが自分の中で言葉やフレーミングされて、アウトプットされ、認知されて、一部になる。歪になりそうなものは吐き捨て、私となれるものに関しては、あたかも最初から知っているそぶりで話し始めてしまいそうなくらいな (反対にいつでも拒絶できるから) 気持ちがある。
眠かったからかもしれないけど、読んでいても全くに入ってこなかった文を、アラン・セクーラが一体どんな写真を撮っているのか、そして文章内に出てくる写真家はいったいどういう人なのか、という、触覚が伸びるままの角度で、後半の気になるところから読み進めてみたら、大変に面白かった。ここでも、甲斐さんの解説が大変に優しく、理解促進を包んでくれました。
“「忘れ去れた」場所(人が見向きもしないような場所)と撮る。ビル・オーウェンズ
“資本主義下において労働は安全なものとはなり得ないという結論”
“フィリップ・スタインメッツによる6巻本の、彼自身と親戚の社会学的「肖像」でも共有されている。誰かが間違いを犯している)(1976年)と題されたその作品総体は、数年にわたって撮影された600枚以上の写真によって構成されている。写真〔の被写体たち)は明るく照らされ、皮肉に満ちた出来事や物の細部であふれており、ラッセル・リーの写真を想起させる。スタインメッツが多大な注意を払っているのは、個人的なスタイルの美意識、服装と身ぶり、室内の装飾である。彼によるキャプションは、社会学的な論争から個人的な逸話に至るまで様々である。この本は、家族アルバムと上品に手作りされた様々なコーヒーテーブル・ブック(部屋の飾りに使われるような大型の豪華本)の興味深いハイブリッドである。家族アルバムの物語のスパンは時間的に圧縮され、取材と暴露の猛烈な強度を生み出している。”
“親密な事柄を取材する一方で、スタインメッツは郊外の中流階級の家族生活の提喩的な表象を差し出す。”
“これらのピクチャー・ブックは一連の断続的な演劇的出会いの産物である。つまり、美術家が「家族を訪ねる」のである。いくつかの機会は伝統的な家族アルバム写真にふさわしい幸先の良い瞬間(誕生日や家族でのディナー)であふれている。ここでスタインメッツは内部の者であり、家族の論理の枠内で彼は役目を果たし、写真を撮ることを期待され、時にはそうするように頼まれもする。”
“最終的には、作品それ自体が家族のイベントとなる。スタインメッツは自身の本を何冊か持って両親を訪ね、キャプションをテープレコーダーに吹き込むように依頼した。ロジャー・ウェルチがその一例であるように、彼以外の美術家や写真家たちも、家族のアーカイヴを用いてこの種のことを行ってきた。違うのは、スタインメッツは記憶や郷愁それ自体には特に関心を持っていないということである。”
“6巻本の最後は、彼の元妻の二度目の結婚を扱っている。スタインメッツはドレス・リハーサルに姿を現す。だが、何者として?ゲスト、侵入者、公式カメラマン、覗き魔、それとも過去の亡霊?彼の妻の新しい姻戚は困惑しているように見える。それらの写真には不条理さの奇妙な感覚、うまく身につけることができてないパッケージ化された役割の奇妙な感覚、そして、消費者の儀式の奇妙な感覚がある。”
この方、アラン・セクーラさんとも同時代に活動しているらしく、何かを語るにあたり、やはり自分と同世代に生きている人と、というのは、当たり前にそうなりますよね……と。つまりは、言葉を知らないだけで、実は伝えたいことがもっと別であるはずなのに、その言葉を使えるってところの範囲中で知っていて近い言葉を選んで伝えてる。だから、もっと違うかもしれないのに…語るべく言葉を知らないだけなんじゃないかなって思うのは、よくあること。ワークショップにしても、ワークショップってこういうものなんだっていうのでやってて、でも、それ以外を知っていないと、それだけをすることがワークショップなんだと思い込んでしまう。フィリップ・スタインメッツのやっていることは大変に嫉妬するほどに共感するし、理想的と感じるけれども、ここに文章として乗っているのは、それはアサン・セクーラにとって身近な存在であったことっていう側面もあったってことはないのかな…?とふと、感じました。表現することに、どうしてもその環境と、時代が関係することは、それ自体は私が生きている証拠・・・ですもんね。一人じゃなくて、みんなで生きている証拠というか。そういう意味で、同志で組織を作ったり、1つの団体をつくるってことは、自然とそうなるものなのだなぁとも。
ー 解説
“そのような芸術写真観が資本主義と共犯関係にあることを問題視するのである。1839年に写真の発明が公表されると、多くの人々は、写真は芸術にはなり得ないと考えた。実際、写真という新たな視覚表象の技術がその威力をもっとも発揮したのは、芸術からはおよそかけ離れた分野であった。ところが「写真プリントを特別扱いされた商品へと変容させ、その活動の背景をかえりみることもなく、写真家を天才となる能力を秘めたひとりの自律的な「作家」へと変容させることによって、写真を高級芸術の地位へと持ち上げようとする近年の企て」が、写真をロマン主義的芸術観へと結びつける。論文が発表された当時、シャーカフスキー率いるニューヨーク近代美術館の写真部門はそのような企てを推し進める中心的機関であった。写真作品は写真家の内面の表現である、という考えにシャーカフスキーは懐疑的だったが、天才的写真家の存在は否定しなかった。”
天才・・・。とは、能力というより、きっとジャンルを関係なく用意に飛び越えてしまうこと、、、?現代ならば、もしかして価値が高まった写真を、さらに変えていける人が天才・・・なんじゃないかしら。
“多くは、セクーラの大学時代の知り合いである。彼らとの交友は、セクーラのその後の批評家、そして写真家としての活動に決定的な影響を与えることになった。「ドキュメンタリーを再創案する」で論じられる作品には大きく三つの傾向がある。ひとつめは、ドキュメンタリー写真というジャンル、さらには、現実の出来事を描写するメディウムとしての写真の能力それ自体を批判的に吟味しようとする傾向であり、ロスラーの(二つの不適切な記述システムにおけるバワリー)(以下(バワリー)と略)がそれを代表している。バワリーとはマンハッタンにある通りの名前である。通俗的なドキュメンタリー写真であれば、スラム街として悪名高いバワリーのそれらしい様子を見たいと感じる読者の期待に応えようとし、例えば、路上で酔いつぶれる浮浪者の写真などが使用されるだろう。それに対して、ロスラーの(バワリー)では写真と単語の並置によって、そのような期待をことごとく裏切ることが意図されている。その結果、それは「ドキュメンタリーのジャンルに対して容赦なくメタ批評的な関係を持つ」(41頁)作品になるとセクーラは述べる。”
「銀座」なら銀ブラしてる人、「秋葉原」ならオタク。「渋谷」はギャルで、「新宿」はゲイ。「池袋」はウエストゲートパークな感じで、「巣鴨」はおじいちゃんおばあちゃん。容易に街と想像が、出来上がってしまっていて、そうであると思い込んで街を歩いている節がありますが(ノーアップデートな古いすぎる情報ですが)、そうじゃない光景を見た時に「渋谷も変わったね〜」「ギャルっていなくなったんだね」「アキバって、こんな感じだったっけ?」と、自分の中にある街が、ちょっと壊れたり、平板化したり・・・あとはそう思い込んでいるだけな自分だったと反省したり。日本に忍者がいるとか、海外は危ないとか、雨で残念とか、お金がなくて暮らせないとか、ゴミは捨てるものとか、たしかに、そう細かく照らし合わせて見れば ”そのような芸術写真観が資本主義と共犯関係にあることを問題視するのである。”は、同じようなメロディーで、問題視されるべきな気がしてきた。(超感覚なつらつら)
● ジェフ・ウォール
なんか、一際に眠くて、最後読み切らなきゃという変な思いから、むずかしかった・・!( いつも本は後半になると、ペースダウンするのは、なんでだろう〜なんでだろう〜 気合いと好奇心の問題でしょうか ) でも、ジェフ・ウォールの写真をいくつか見てからは、なーるほど、とはなりました。そして、ゆーーくり頭を整理して読んでみると、すごい、これまた面白いのです。もう一度、読まないとと思うくらい。
“1950年はおろか1960年に至っても、重要な芸術写真の作品が100ドル以下で購入できたという事実は、驚きに値する。このことが示唆するのは、芸術写真の美学的構造の内的な複雑さにもかかわらず、資本主義社会においてそれはまだ芸術として認知されていなかったということである。”
これは、今になっては、うれしき水たまりじゃないだろうか。
“つまり「フォトードキュメンテーション〔写真による証拠文書の作成〕」。だがそれがそうなるのは、新たな種類の写真的事物の外観を描写するという避けられないプロセスと、同様に避けられない(写真という)対象=物体を作るというプロセスのあいだのこうした矛盾こそが、写真がある種の芸術 ー芸術の概念がその主題となっているような芸術ー のモデルになることを可能にしたのである。”
ゆーっくり何回も読んで理解してみると、すばらしき捉え方。写真そのものの在り方が、芸術としてすでに面白いということ…ですよね?どんな像であろうとも。
“イメージの領域における産業革命を代表するものとして、写真の登場がモダニズムの歴史的プロセスを始動させたというのはよく言われることである。だが写真自体のモダニズムの言説への歴史的発展は以下の事実によって決定づけられてきた。それは、より古くからの諸芸術とは異なり、写真は描写なしで済ますことができず、それゆえ明らかに、写真が最初に提案したと言えるかもしれない冒険に自らは参加することができない、という事実である。”
写真が、モダニズムの歴史的プロセスを始動させた、写真が生まれなかったらと想像すると…なんか割にいい世の中でもあったんじゃないかと思ってしまうのは、私だけでしょうか。でも、写真でなくとも印刷技術あたりから、限りなく写真に近い何かが生まれていたはずですよね。必要というか、人間の欲望というか、、、。欲望なき写真ってあるんだろうか。”写真的事物の外観を描写するという避けられないプロセス” が、ある限り、、、と思いつつも、世界をとらえている身体がある限りは、なんら変わりないはず。。。そんなに写真が”写している”ものは実は大きくないと思ったりも。もっと身体的なもので。( スマホで打つ文と、パソコンで打つ文は、変わるんだけど、それ以上に肉体があること時点の方が、無意識的に大きいというか… だから、文や視覚で理解しちゃいけないし、しきれないとも ) と、スマホで打ってからパソコンに戻ってみてもそう思う。(・・・なんの話?
“それゆえラディカルな脱構築は「無感覚的II非美的なもの」のモデルの追求という形で具体化した。デュシャンは1920年までにこの領域の見取り図を描いていた。ゲルハルト・リヒター、アンディ・ウォーホル、マンゾーニ、ジョン・ケージらとともに40年後に浮上した新たな批判的即物主義の数々にとって、デュシャンの影響は決定的なものであった。無感覚的=非美的なものはレディメイドーあらゆる外観、形態、痕跡として現れる商品の中にその象徴を見出した。”
写真がまだ食べ始めだった頃、同じように、食べ始められたものが、空き瓶干すヤツだったり、埃だったり、自転車だったり、の…?
“正典(キャノン)となったモダニズムの趣味、スタイル、芸術のあらゆる尺度を侵犯するような、当を得た実用的イメージ、描写、造形、物体を求めて、労働者階級、下層中流階級、郊外在住者、そして底辺層の環境が念入りに探索された。初期のポップ・アートは時に、もっとも完璧で、形而上学的なまでに凡庸なイメージを見つける競争であるかのように見える。凡庸なイメージは、近代芸術において、真剣さ、専門的能力、反省性として知られてきたもののあらゆる面が放棄された後でも、文化が継続可能であることを証明する暗号なのである。”
念入りに捜索されての、アーバスやらアウグストサンダーなのでしょうか。って、アーバースはあとの世代だから…、サンダーはその流れというか、それを知っててやったいたのかが気になるから、知りたいなぁ。アーバスは当事者として、不思議に思ったのだろうとか、映画を見た限りは思いますが。。。
ふと思えば、限りなく情報の少ない世界だから( 当時デュシャンもフランスでは「だれ?」って感じに近かったらしいし ) そんなことはないか。。。その時代を生きていたことが、きっとそうさせたんですよね。ポロックとヴォルスが、遠い国で自然と生まれたみたいな。時代ってのは。。。
“空虚なもの、偽物、機能的なもの、野蛮なもの、そうしたもの自体はもちろん、1960年の時点で芸術として全然新しくはなかった。それらはみなシュルレアリスムを通してすでにアヴァンギャルドの修辞的表現となっていた。しかしながら、ポップ・アートによって生み出された視点からは、それ以前におけるこの問題の扱い方は、真正な芸術に宿る変容作用についてのロマン主義的な概念に強く固執しているように見える。無感覚的=非美的なものは芸術へと変容させられるが、それはショックによって破断された線に沿っている。無感覚的=非美的なものが真剣な作品の中に出現することによって引き起こされるショックは、真剣さそれ自体のアウラによって落ち着きを・・・”
なんで、こんなにも何回も読まないと頭に入ってこない文章なんだろう。それは知っている概念がそもそも違うみたいな感じで、「写真」をそもそも違うものだと感じてる気さえする。。。”無感覚的=非美的なものが真剣な作品の中に出現することによって引き起こされるショック”は、ディペイズマン的なところで、でも、写真はそれすらも「アウラ」がまとって落ち着き(ワンクッション挟んでいる)を得たことで、1つのジャンルになってる・・・・?
だから立体的なものが存在することとは、違う世界が写真として生まれているのはその「アウラ」のせいなんだ。っていう理解でいいかしら。となると、やっぱり、ベンヤミンを読まなくては・・・という。くりかえし。
● ロザリンド・クラウス
1分間、1枚の写真を見て思いついたままを話すという映像を作ったAgnes Varda。おもしろい!これは、やりたいなぁ。結構理想に近いかもしれません。しかも、その写真のどれもが写真家、作家、もしくは報道カメラマン?が撮ったでだろう写真で。で、鑑賞者も有名な作家、写真家本人から、ビザ屋の店員まで幅広いのも、やりたいことが分かる。
面白いコメントは、大家族らしき子供と親御さんらしき人が写ってる写真を見て、全員の思いついた架空の名前を言っていく年配の女性の声…。写真はそういう個人の妄想捏造を促すような役割もあるんだろうとも思うと、複製できること( アート作品だってこれだけ知れ渡っているのは、作品資料として掲載できる写真があるから ) は、もっと再評価されるべき利点だったりするのではなかろうか…とも。オリジナルプリントももちろん素晴らしいけど、複製できることの素晴らしさを、写真が生まれた時のことを思うと、もっと称えてあげたい気持ちに。
そして、シンディーシャーマンも、既存にあるイメージ(ポスターであり映画のシーンであり) を、模倣してパロってるというのは、顕著に写真的?というような話で。アーヴィングペンのスティールライフな構図も、ルネサンスからの構図であったり、バロック的だったり。“複製できる”良さが、美術的評価軸の中では、評価されにくいならば、そこを離れて、写真を素直に「焼き増しできて嬉しいね!」と、みんなにあげて笑いたいなと。なぜ1枚しか、なかったりしなきゃいけないんだろうか。というところを思うと、複製芸術のベンヤミンをちゃんと読みたい・・・なー。読みたいものばっかりだ。
“ある時点で写真は、その偽のコピー、ー内的で本質的なつながりによってではなく、機械的事情によってのみ原型に類似しているようなイメージー としての不安定な地位ゆえに、原型とコピー、オリジナルとフェイク、一次的複製と二次的複製、そういったもののシステム全体を脱構築する役を果たした。”
というのは、すごいことなんじゃないだろうか(という感想がとにかくチープ) 。オリジナルとフェイクのシステムを脱構築する役割とは、写真にしかできないことですもんね。模写してってのはあるかもしれないけど。3Dプリンターもしかりですが。。。昔の人が3Dプリンターの存在を知ったら、何を書くやら。
“(ひとつのイメージのための1分間)は、鑑賞者に空想の物語を投影してもらうために、写真を孤立した状態で示し、さらにそれは、ある種の大衆意見調査を支持して、批評的能力という観念を放棄する。その点でこの番組はシリアスな批評の厳格さからはこれ以上ないほど隔たった位置を占めている。だが、そのような立場を取ることによってそれは、そうした批評が、写真という領域に対してイレレヴァンス、まったく見当違いである可能性を提起する。”
“孤立した状態” …だからこそですよね。。。うーむ。写真が孤立するという状態は、写真としては結構な特別な状況というか、展示されていたとしても、たとえばアルバムなり、フレームに入れたりしても、それは完全なる孤立ではなくて、、、映画に没頭でいるような孤立感というのを「写真」でやってみるというのは、プリントを展示するよりかは、写真らしいのかな。映像のイメージとして見るような。そこには”サイズ”が消えて、”もの”も消えて、古いか新しいかも消えて、だからこそイメージだけに集中できる。そんな像だけを見つめることができた1分間だった気がする。
< 解説から >
“現実の痕跡としての写真と、現実の記号化としての写真。両者の違いは無視することができない。「写真的なもの」の説明においてこのような違いが生じるのは、写真の様々な性質のうち、強調される点が両論文で異なっているからである。すなわち、前者ではフィルムに投影された像を撮影者の意図とは無関係に写し取る写真の機能が、後者では、その写し取りのためには、カメラによるフレーミングが必要であることが重視されている。”
“同論とも強調される写真の特質は、写真というメディウムが、芸術作品のオリジナリティという考えになじまないということである。”
おもしろいよね。そもそもが、芸術作品のオリジナリティという考えにはなじまない・・・。じゃーなんでアートになったんだろう・・・か。そして、そういう考えになじまいものは、アートの仲間入りすることは、たくさんあるんじゃないかなーと。えっそれ、どこにでもあるよね?とか言うものが。いったらキリがないんだけど。アートがどんどん、いろんなものを食べて大きくなっていく。もう、サインするってなんだろうとか。。。人間自体も食べられちゃうんじゃないかってくらい。
“シャーマンは、映画でよく見かけるような、型にはまった役柄を自ら演じ、それをスチル写真という形式で発表する。何か特定の映画が参照されているわけではなく、演じられている場面に明確なストーリーはない。ポイントはあくまで「いそうな」登場人物、「ありそうな」場面を作り出すことにある。その結果、シャーマンの写真作品はすでに複製物であるものをさらに複製したもの、つまりシミュラークル(オリジナルなきコピー)となる。”
すごい近いっ・・!オリジナルなきコピー。。。清水ミチコさんの作曲法じゃないですか。ありそうな人、いそうな人。モノマネ・・・。それをすることって、、、つまり私たちが”すでに知っていること”をやってるんだよね。どこでそれを知って、なんで多くの人が知っているのか、という点でかなり社会性、大衆生を感じちゃいます。そして、なぜそれが面白いかってところが、実は私たちは社会や世間を"ちゃんと"歪んだものとして見れているからでしょうね。
“1982年の論文「写真の言説空間」でクラウスは、ティモシー・オサリヴァンによるアメリカ西部の地質学調査の記録写真など、元々美術作品として作られたわけではない19世紀の写真が、美術館のコレクションとして展示される状況を批判している。写真研究者たちは「芸術家」、「経歴(career)」、「全作品(oeurre)」といった美術史に基づく概念を、19世紀の地誌的写真(地形を記録した写真)に当てはめようとしてきた。”
“クラウスは、19世紀の地誌的写真は「風景(landscapes)」というよりは「眺望(views)」であり、それを見る人は撮影者の名前などは気にしなかったこと、そして、それらの「眺望」は多数収集され…”
なーるほど。ラウンドスケープというと、美術的な視点だけど、ビューとすると、歴史的、考古学的?な、資料としての視点だから、、、。一緒くたには、ならないけど、なってるよね。そこに価値を見出しているということは、写しているものよりも、やっぱり複製できるものとしての芸術性に惹かれている部分がある・・・ってことかしら。
“ビデオやその他の様々な映像技術によって「時代遅れ(obsolescence)」となることで、写真はメディウムの再創案のための手段になる、とクラウスは述べている。例えば、スライド映写機(リバーサル・フィルムに後ろから光を当てて、スクリーンに投影する装置)を用いたコールマンのインスタレーションは、写真のそうした活用の例とされる。ただし、2017年の状況に基づく視点から、クラウスの主張に異論を唱えておくならば、写真自体が「時代遅れ」になったというよりは、写真技術とその利用の特定の側面が時代遅れになったと言うべきだろう。確かに、スライド映写機やネガ・フィルムに日常生活で接する機会はほとんどなくなり、もはやそれらを過去の遺物ではないものとして見るのは難しい。”
近い・・!!私の知りたいことに、近いですね。コールマンって一体、誰のことなんだろう。アウトドアやん。見てみたい。 ”過去の遺物”としてしか見れなくなってしまう。。。その状況。。。近いなー。しかし、過去をやりたいわけじゃないし、ノスタルジックに浸ることが表現ではなくて、写真ってなんだろう?っていう中で、実はスライド的なものが写真だったと、気付いたりしたら、それはもう古くはないんですよね。。。ついつい、レトロに浸りがちです。人間の脳は。
“「写真とシミュラークルについての覚書」の結論部でクラウスは、「シリアスな批評」が「写真という領域に対してまったく見当違いである可能性」に言及している。ここで表明されているのは、もし大衆的なメディウムとしての写真がそのような批評とは無縁の場所で生産され、消費されているのだとしたら、自分が書いているような批評は、写真という存在について何か決定的な取り違えをしているのではないか、という懸念だろう(自分は写真「について」は書いていない、という後の主張の源はここにある)。この懸念は理由のないものではない。少なくとも、ブルデューの理論に従えばそうなることになる。なぜなら、ブルデューの調査によれば、写真をもっとも愛好しているのは、高級芸術や哲学などは理解せず、理解したいとも思わない中間層だからである(ちなみに、これは現在の日本にもある程度当てはまることではないだろうか)。”
おもろい!写真をもっとも愛好しているのは、中間層。。。が、ピッタリきちゃうわけですね。確かに、貧困層にはカメラは高級すぎるし、有名な写真家のみなさんは、ある程度、どころかかなり裕福な家庭で生まれそだった中で、自然とカメラが家にあり、という中だし、きっともっとブルジョアな方々は自分で写真を撮るって行為はしないかもしれない。礼節として、勝手にいろいろ写真を撮る行為というのは、けっこう失礼に当たる場合もあるかもしれないし。
だから、芸術に対するようなシリアスな批評が、実はそこに触れていないものだった・・・から検討違いだったんじゃないかっていう。駄菓子について真剣に成分分析とかから考察していても、駄菓子はそもそも子供たちが食べるものなんだから、そこの意見を踏まえていないと、批評になってないじゃないかみたいな・・?健康に悪くたって、意味がなくたって、そもそも子供たちにとっての駄菓子は、そういうものじゃないんだからっていう。
もー内容、濃くて、読むの面白すぎて、、その分、アウトプットからの消化は、胃もたれまではいかないけど、快便難産って感じて、大変でした。